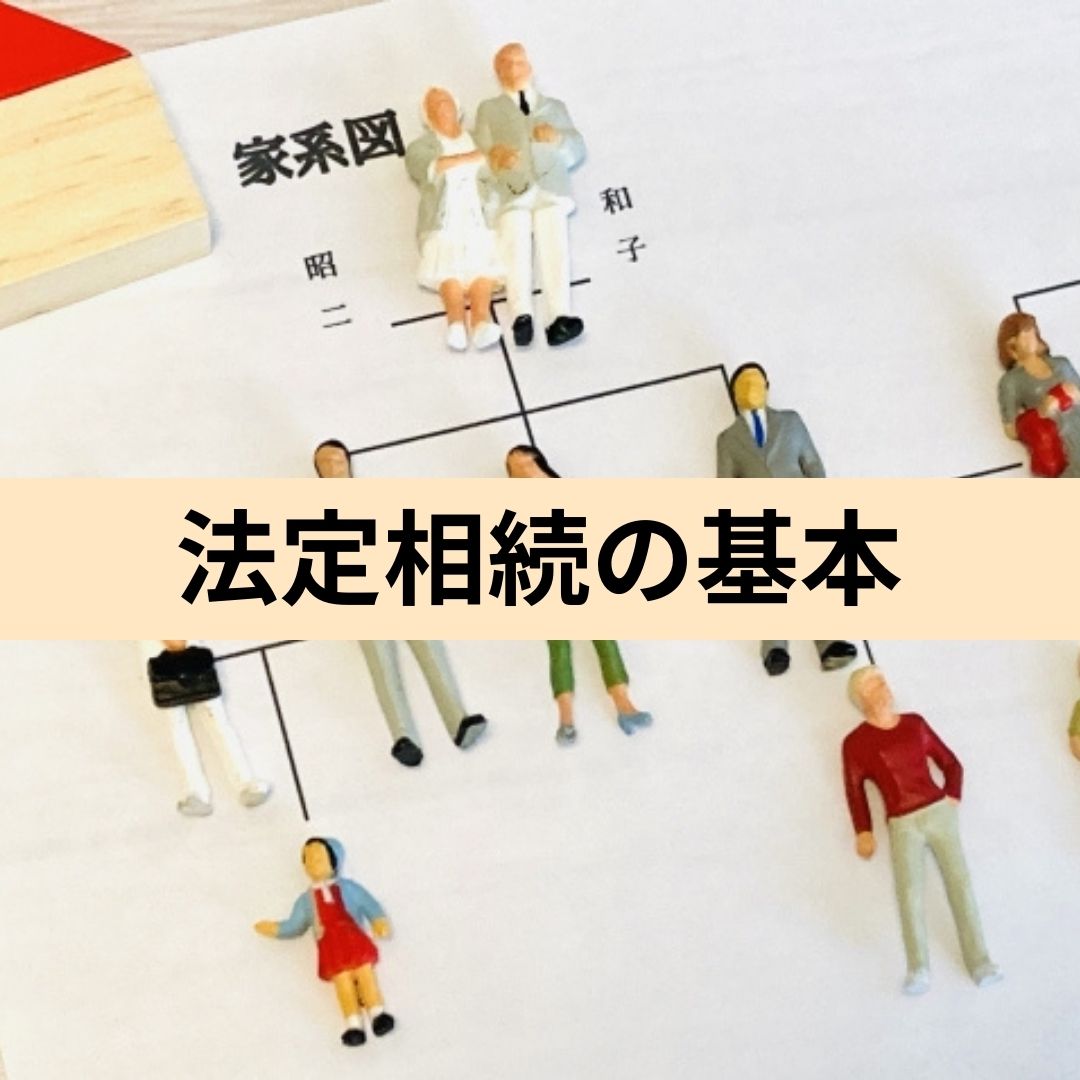身近な人が亡くなったとき、遺産をどのように分けるのかはとても大切な問題です。
遺言書がない場合、遺産は「法定相続」に従って分配されます。
この記事では、法定相続の基本的な仕組みについてわかりやすく解説します。
1. 相続開始の根拠
相続は、被相続人(亡くなった人)が死亡した時点で開始されます。
これは民法第882条に基づくもので、「相続は、死亡によって開始する」と明記されています。
つまり、死亡届が受理されると同時に相続が発生し、相続人は遺産を受け継ぐ権利を持つことになります。
2. 法定相続とは?
法定相続とは、民法によって定められた相続のルールです。
遺言書がない場合に適用され、被相続人の財産が相続人に自動的に分配される仕組みです。
3. 相続人の順位と割合
法定相続では、相続人の順位が決まっています。
(1)第一順位:子(直系卑属)
被相続人に子がいる場合、子が相続人になります。複数いる場合は均等に分配されます。
(2)第二順位:直系尊属(父母など)
子がいない場合、被相続人の父母などが相続人となります。
(3)第三順位:兄弟姉妹
子も直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者(夫または妻)は常に相続人となり、上記の順位に応じて財産を分配します。
4. 法定相続分の割合
法定相続人の組み合わせによって、相続分の割合が異なります。
- 配偶者と子がいる場合 → 配偶者1/2、子1/2(子が複数いる場合は均等に分配)
- 配偶者と直系尊属がいる場合 → 配偶者2/3、直系尊属1/3
- 配偶者と兄弟姉妹がいる場合 → 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
5. 遺留分について
法定相続人には最低限確保される「遺留分」があります。
たとえ遺言書があったとしても、特定の相続人に全財産を譲るような内容であれば、遺留分を請求することが可能です。
- 子・直系尊属の遺留分 → 法定相続分の1/2
- 兄弟姉妹には遺留分なし
6. 遺贈について
遺贈とは、被相続人が遺言によって特定の個人や団体に財産を譲ることを指します。
遺贈を受ける人を「受遺者」と呼び、相続人でない人でも財産を受け取ることができます。
遺贈には以下の種類があります。
- 特定遺贈:特定の財産(例:土地や株式など)を受遺者に譲ること。
- 包括遺贈:財産全体の何割かを受遺者に譲ること(例:「全財産の3分の1を○○に遺贈する」)。
遺贈をすることで、相続人以外の人にも財産を渡すことが可能ですが、相続人の遺留分を侵害しないよう注意が必要です。
7. 相続登記の義務と期限
2024年4月1日から、相続による不動産の所有権移転登記(相続登記)が義務化されました。
相続登記を行わなければならない期限は、相続開始を知った日から3年以内です。
これを怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記を速やかに行うことで、不動産の所有権が明確になり、後のトラブルを防ぐことができます。
8. まとめ
法定相続は、遺言書がない場合に適用される民法上のルールです。
誰がどれくらいの割合で相続できるのかを知っておくことで、相続トラブルを防ぐことができます。
また、遺言書を作成すれば、法定相続とは異なる形で財産を分配することも可能です。
遺贈を活用することで、相続人以外の人にも財産を渡せるため、事前にしっかりと計画を立てることが大切です。
また、相続が発生したら不動産の相続登記を3年以内に行う義務があるため、早めに手続きを進めることが重要です。
相続についてお悩みの方は、専門家に相談してみるのも良いでしょう!
 お気に入り
お気に入り